
令和7年度は「AIと広告」をテーマに法政委員会勉強会を開催します。
全5回の勉強会も今回で最終回となりました。これまで、本勉強会ではAI技術の進展状況やそのリスク、必要なガバナンス、そしてAIの爆発的な進化と、最新のAI動向を扱ってきました。最終回はその集大成として「人間中心のAIのアップデートと創造性の進化」をテーマに、AI技術の急速な進化の中で問われる「人間の普遍的な価値」と、組織や社会がいかにAIと共創していくべきかについて、哲学的な背景から実践事例まで、多角的に学びました。
AIに対する「普遍的な人間の価値」の認識は西洋・東洋で異なる
今年のAI技術の進化はすさまじく、GoogleのGemini 3.0やNano Banana Pro、(その後に続いたGPT-5.2 のリリース等)による技術の飛躍的向上など、1年前に語っていた未来予測が数ヶ月で陳腐化してしまうほどのスピードで変化が起きています。トップ研究者ですら「なぜこれほど早く実現できたのか」と驚くような技術が、毎月のように登場している状況です。
来年もこの加速度的な進化は続くでしょう。そこで重要になるのは、技術のキャッチアップと並行して「普遍的な人間の価値とは何か」を問い続けることです。
AI時代における人間の価値を考える上で、今年9月に開催された京都哲学研究所主催の「第1回京都会議」での議論は示唆に富んでいました。世界中の哲学者や産業界のトップが集ったこの会議のテーマは「人工知能(AI)時代にこそ必要となる、社会の根幹たる価値観や価値についての議論と対話」であり、「今こそ世界に哲学を」という研究所の理念にもとづきながら、AI時代の人のあり方や価値について活発な議論が行われました。
この会議で京都大学の出口康夫教授が提示した「西洋・東洋での『人間』の捉え方の違い」が非常に面白いテーマでしたのでご紹介します。西洋的な価値観において、人間は「分割できない個」であり、「できる存在」と定義されます。ニーチェの超人思想のように能力(できること)こそが人間性であるならば、その能力を凌駕しようとするAIは脅威となります。よって、西洋ではAIロボットといえばターミネーターが想起され、それに対峙するのは英雄的な人間であるジョン・コナーとなるのです。
一方、東洋的な価値観では、人間は「関係性の中の自分」であり、本質的に「一人では生きられない、できない存在」です。欠落があるからこそ、他者と協力し合います。日本ではAIロボットといえばドラえもんであり、ドラえもんに対峙するのはのび太です。のび太は「できない存在」ですが、かけがえのない人間として愛されています。この弱さやできなさこそが、AIを仲間として迎え入れる土壌となるのです。
「人間中心のAI」を2軸からアップデートする
人間に寄り添うAI、すなわち「人間中心のAI」という概念の起源は、1999年のISOによる「人間中心設計」にあります。その後、AIの社会的影響力の増大に伴い「リスク管理・倫理・ガバナンス」の文脈で人間中心のAIが語られるようになりました。しかし今、スタンフォード大学などが提唱するように、「人間の能力拡張」へと焦点が移りつつあります。
このような中、今「人間中心のAI」を2つの軸でアップデートすべきです。
〇横軸:ガバナンスから創造性の進化へ
「人間中心のAI」において、近年ではガバナンスの強化が意識され「人間に害をなさないAI」という受動的な設計が進められてきました。一方で、今後の人間中心のAIは、受動的な段階を超え、人間が主体性を持って成長し、創造性を拡張していく方向への進化が必要です。
〇縦軸:ユーザーから生活者へ
オリジナルの「人間中心設計」では、人間とはすなわちシステムの利用者である個人ユーザーという狭い定義でした。一方で、例えば「AIでエネルギー消費を最小化する」「都市構造を最適化する」「犯罪を防止する」など、AIの利用により社会的な変化が生じる時代では、AIを直接利用していない人もAIの影響を受けることとなります。よって、AIの個人ユーザーだけでなく、組織や社会、生活者全体を対象として「人間中心のAI」を設計していく必要があるのです。

AIによる認知能力低下に陥らないために「サイボーグ型」でAIを利用する
一方で、AIの負の側面に関する研究やレポートも増えています。2025年に入り「AIを使うと人間の認知能力やチームのパフォーマンスが下がる」という研究結果が多数報告されるようになりました。
MicrosoftとGartnerの研究者が行った調査では、AIのアウトプットに依存することで、知識労働者の認知能力が減退する可能性が示唆されました。最近は、このような問題を「コグニティブ・オフローディング」という用語で表現されたりします。 AIを使うことで創造性を広げていくという理想がありつつも、実際に様々な分析をしていくとAIが人間の能力を衰えさせているという課題が浮き彫りとなっているのです。
この問題に対しては、「AIを道具としてではなくパートナーとして使う」ことが解決策となります。例えばAIから人間に質問させることで人間側に負荷をかけ、人間側の創造力を高めていくような使い方です。
ペンシルベニア大学のイーサン・モリック准教授は、AIとの協働モデルとして「ケンタウロス型」と「サイボーグ型」を提示しています。
ケンタウロス型(分業型)は、下半身は馬、上半身は人のように、「ここはAI、ここは人間」とタスクを切り分けるスタイルです。効率化には寄与しますが、認知能力を下げるリスクがあります。
対してサイボーグ型(協働型)は、AIと人間が一体化して思考するスタイルです。AIと対話し、ともに悩み、AIに「問いかけさせる」ことで、人間の思考を深め、品質を高めます。
重要なのは、AIを作業の代行者にするだけではなく、自分に質問を投げかけ、気づきを与え、アイデアを引き出してくれるパートナーとしてもAIをデザインすることです。
博報堂DYグループの「主体性を引き出すAI活用」実践事例
博報堂DYグループでは、この協働を行う「サイボーグ型」のアプローチに近い実践を行っています。一例として、従業員インタビュープログラムをご紹介します。
従業員インタビュープログラムでは、インタビュワーとなるかわいいキャラクターAIが従業員にインタビューを行います。アンケート形式ではなくAIが「仕事で何にこだわりを感じるか」「嬉しい瞬間はいつか」などと聞き、従業員はこれらの質問に答えていきます。AIに「聞かれる」という体験を通じて、従業員自身が気づいていなかった情熱やこだわりが言語化されます。これにより、エンゲージメントサーベイでは拾いきれないリアルな思いが可視化され、経営層と従業員の新たな対話のきっかけも生まれます。
もう一つは、「AI逆メンタリング制度」 です。AIをチームの意思決定に使うとパフォーマンスが下がるという研究が存在する中、実はチームに熟練者がいるとパフォーマンスが上がるという結果も明らかとなっています。AIとシニア層などの熟練者の組み合わせによりハイパフォーマンスを生む可能性があり、実際にガートナーは2028年にシルバーワーカーの黄金時代が来ると予測しています。
しかし現状、シニア層のAI利用率は低いのが実情です。そこで博報堂DYグループでは、役員全員に若手社員を「AI家庭教師」としてつける逆メンタリング制度を実施しました。役員ごとにカスタマイズした宿題を出し、毎週対話することで、経営陣自身に「AIで何ができるか」をインプットしたのです。これにより、トップの意識を意識に火をつけることに成功し、グループ全体で8,500名規模のAI人材育成へとつながっています。

今回は、「AIと広告」をテーマとした勉強会の最終回として「AI時代における人間の創造性をどのように高めるのか」「組織や社会がいかにAIと共創するべきなのか」について学びました。AIが出した答えを鵜呑みにせず、「自分はどうしたいのか」「さらに良くするにはどうすればいいか」と主体的に関わるプロセスによって、個人の認知能力は高まり、企業の生産性は向上し、市場や社会を変える新しい価値創造へとつながっていきます。 AIの進化は激しいですが、それに圧倒されるのではなく、主体性を持ち続けることこそが、これからの企業と個人に問われているのです。
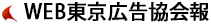
 第5回 人間中心のAIのアップデートと
第5回 人間中心のAIのアップデートと