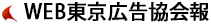葛西 薫 氏(アートディレクター、㈱サン・アド顧問)

文華印刷、大谷デザイン研究所を経て1973年㈱サン・アド入社後、長年にわたり、アートディレクターとして第一線で活躍。サントリーウーロン茶、ユナイテッドアローズ、虎屋をはじめとする数々の広告制作、アートディレクションのほか、CI・サイン計画、映画・演劇のグラフィック、タイトルワーク、エディトリアルデザインなど活動は多岐にわたり、多くの実績を上げてきた。東京ADCグランプリ、毎日デザイン賞など受賞歴多数。桑澤デザイン研究所、東京造形大学、多摩美術大学の客員教授をつとめるなど、後進の育成にも尽力している。様々な広告賞の審査にも関わるなど広告の発展に寄与し、長らく業界全体を支えてきた功績は贈賞に値する。
対談 「伝える」と「伝わる」のあいだに
内藤 裕子 氏(フリーアナウンサー)
内藤:本日の聞き手を担当します、アナウンサーの内藤裕子です。私は2017年までNHKのアナウンサーとして、2018年からはフリーアナウンサーとして活動をしています。演題の『「伝える」と「伝わる」のあいだに』というテーマについて、私自身も日々このテーマと格闘しているため、本日を非常に楽しみにしておりました。

葛西:まず初めに、受賞へのお礼を申し上げたいと思います。
僕がこの仕事を始めたきっかけは、「文字」に興味を持ったことから始まりました。そこから「デザイナー」になりましたが、専門的な教育を受けないで仕事を始めて、いつの間にか五十数年になりました。自分がこの仕事に向いているのか、長い間やっていけるのか、という不安はずっとありましたが、それがエネルギーになって、何かしないわけにいかないという思いで続けてきました。
もう一つは、自分の中に教科書というものはなかったのですが、5年、10年、20年、30年先輩たちの仕事や活動を見ていて、それが何よりも僕にとっては勉強になり、それらの助けがあったからやってこられたと思っています。
そして、その時々の仲間たちがいて、この仕事のおかげでさまざまな分野の方たちに知り合うことができ、ともかく目の前にある仕事をありがたく、全力で懸命にむかうということを続けてきたと思います。
この度このような賞をいただいて何よりも感謝したいのは、諸先輩方と仲間たち、それからこの時代です。僕がやってきたこの70年代から今日まで時代が、とても幸運だったと思います。とても幸せな時代を過ごさせてもらって、その上にこのような賞をいただき、仲間と一緒に、先輩たちと一緒に受け止めて、感謝申し上げたいと思います。
内藤:私は、葛西さんの代表作のひとつであるサントリーウーロン茶のCMが始まった頃、小学1年生でした。その頃の自分のことや、家族だんらんの思い出、過ぎし日の過去の懐かしい風景がよみがえってきました。
葛西:小学1年でしたか。今の大学生の前で話すときにCM映像を見せると、もう生まれる前のことだったりしますね。過去の日本にこういうコマーシャルがあったと話すことがあって、ずいぶんと時間がたったなと改めて思います。僕自身もとても懐かしいですけどもね。
サントリーウーロン茶の仕事に出会う前は、僕らは外国というと西洋に憧れていました。だからモデルは当然のように青い目をした人が多かったのです。そのうちに中国映画とか台湾映画とかが出てきて、僕自身も東洋の素晴らしさに目がいくようになった頃にウーロン茶の仕事に出会うことができました。そこから二十数年間。大変ではありましたが、すべてに数知れない思い出があります。
内藤:今日は、たくさんの思い出のある作品の中から、葛西さんのターニングポイントとなられた作品のお話を伺っていきたいと思います。
サントリー 「アイ ラブ ユー」

内藤:葛西さんが34歳の時の作品です。 私はこのとき小学1年生で、駅のホームで見たのですが、なんて素敵な広告なんだろうと感動しました。この世界観というか余白が、想像させるものがあまりにも多くて、非常に惹き付けられました。
葛西:この仕事の前までは、アートディレクターとして目立たなければいけない、広告は強くなくてはいけない。もっとインパクトを、と求められることも多く、それに応えなきゃと思って必死でアイデアを出そうとしてもなかなか形にならなくて、時間を持て余していたような状況でした。
その頃にこのサントリーのお歳暮の仕事があり、魚住勉氏による「アイ ラブ ユー」というコピーが先に決まっていました。当時の辰馬宣伝部長が魚住さんに、アートディレクターは誰と組みたいか尋ねたところ、サン・アドの葛西と組みたいと僕を推薦してくれて、参加することになったのです。
さて、「アイ ラブ ユー」という言葉が与えられ、どうすればいいのか…。
普通は「アイ ラブ ユー」というと男女の恋などが頭に浮かびますが、ウイスキーを贈るとは何だろう?と考えてみると、それだってもちろんアイラブユーなのですね。
そこで魚住さんと、どんな画にしようかと相談すると、「大正時代のモボやモガはすごくおしゃれで、ロマンチックで良かったね」と。男性はみな帽子をかぶっていて、路上でちょっとすれ違って知り合いがいるとひょいと帽子を上げて、会釈などをするのってなんかいいよね、みたいな話になっていくうちに、空に持ち上げられた帽子というヴィジュアルはどうだろう?というアイデアに結び付いていったのです。
それが本当に画になるかどうかは分からないけれど、まずは提案しようということで、ただ手で帽子を上げているだけのラフスケッチを、おっかないけれど、とても理解のある辰馬さんに提案したところ、「おもしろいやないか」とオーケーになりました。
オーケーにはなったけれど自信がない、でもなんとかしなきゃと思っているところに、その頃大活躍していた菅昌也さんという写真家がおられました。いつか菅さんと仕事をしたいなと思っていてこのアイデアを見せたところ、大いに乗ってくれて一緒にやれることになりました。
ところが、菅さんと打ち合わせをしている時に辰馬さんから電話があり、「このアイデアは悪くはないけど、スタティック過ぎないですか?」と電話がありました。急に不安になられたようでした。僕も不安だけど、もちろん「はい、不安です」とは答えられないので、「絶対大丈夫です」と答えました。あとはもう菅さんに頼るしかない状況でした。
その菅さん曰く「この写真は帽子も大事だけど、帽子を持つ指先はもっと大事。そして何よりも冬の季節感とか“心持ち”みたいなものが大事だ」と。最終的にはあのレンガの東京駅を遠くに臨む場所で、望遠レンズで、光は太陽に一枚パラフィン紙がかかったような、午後3時くらいの夕方でも昼でもない、はかない光がいいみたいなことを言われました。もちろん撮影日にそうなるかは分からないですよね。でも、なんとその日にそのような天気になりまして。彼はテスト撮りもしない、アシスタントもいない、ただ35ミリを構えている横で僕はフィルムを渡す役割だけをしていて、とにかくいい写真が撮れますようにと心の中で祈っていました。
こうして撮影が無事に終了。当時35ミリのポジフィルムで写真を選ぶときは、暗くした部屋で一枚一枚パシャッ・パシャッとスクリーンに大きく投影しながらセレクトしていました。そのときの一枚目の写真がほぼこのポスターになった写真と同じで、ぼーんと大きく出たとき、頭の中ではある程度描いていましたが、僕はもう倒れそうになるくらいに素晴らしい写真だと感動しました。内藤さんが、初めて見た印象をおっしゃったように、この写真には、写真の外にあるものとか時間的にも空間的にも遠くを思わせてくれる何かが映し出されていると思います。
そこに「アイラブユー」の文字を置いてみたら、アイラブユーという言葉の概念が変わったというか、もっと大きな言葉になった気がしました。こういうことがあるのだなと思った、最初の広告の仕事でした。
だから、すべてを見せなきゃいけないとか、全部説明しなきゃいけないというのではなく、世界のごく一部をトリミングして見せれば、あとは見る人がそこから何かを思うはずなので、そこに委ねればいいじゃないかと思って。その見た人一人一人がポスターとリレーションをすることで、広告が完成する。今振り返って思えばですが、そういう思いを持たせてくれたのがこの仕事だったので、この仕事以降、自分が何か今まで悶々としていたものが一つ晴れたような感じがしました。
内藤:本当にその「間」というか、「余白」。この大切さはアナウンスの仕事をしていても思いますが、ついアナウンサーはその余白を埋めようとして、例えば1分だったら58、59秒ギリギリまでしゃべろうとしてしまいます。でも、そうすると余白がなくて伝えたい思いだけが溢れてしまう。しかしやはり余白や間を作らなくてはいけないと、今改めて思いました。
葛西:難しいですよね。僕も『「伝える」と「伝わる」のあいだに』というキーワードをなぜ今日のタイトルにしたかというと、内藤さんがアナウンサーというお仕事をされているので、きっと「伝える」と「伝わる」の間に何か重要なことが起こっているのでは、そういうお話がしたかったのです。
サントリー 「ウーロン茶」

内藤:1983年から始まったのがサントリーウーロン茶の仕事です。広告として初めて新聞に掲載されたのがこちらです。
葛西:実は最初に提案したときは、若い人向けに香港の若者がおしゃれな格好をしていてウーロン茶を手に持っている、ポップなイラストレーション案でした。その絵の打ち合わせに香港に向かう前日に、「待った」の連絡が入りまして。ウーロン茶は脂肪を分解するようなことが期待出来て、今売れ行きが伸びているのは中年層だから、対象は若者じゃないということになりました。
それで一転して考えたのがこのアイデアです。ウーロン茶といえば中国だし、中国といえば何か大陸的なイメージで、そういう図式的な特徴をそのままに形にしました。
僕らの中ではこの人物をウーロン茶おじさんと呼んでいました。
内藤:そしてCMも制作し始めて、本当に中国で作られたお茶なのか?という問い合わせに答えるために「お茶の葉主義」というキーワードが生まれ、その頃に次の転換点となる作品が生まれました。

葛西:はい、当時はとてもきれいで幻想的な、中国に理想に持つようなイメージの広告を作っていた時期でした。ただ、広告主としてはもっと「みんなのもの」になってほしいという思いがあり、CMに活力がほしいという。ただ僕はどうも元気でワーイという雰囲気の広告が作れるタイプでなくて、どうしたものかといろいろなことを考えました。
そこで、そうだ『いつでも夢を』という曲が僕の子どものときにレコード大賞をとっていて有名なデュエットソングだし、それを中国語で歌うのはどうだろうと思いついたのです。
できあがったCMは独特過ぎてどうなのかと思ったのですが、これが話題になりまして、初めてCMがヒットするということを経験しました。親近感を感じられるように、中国の人が日本の歌を歌う、しかも誰もが知っている歌でお母さんも歌えるし子どもも一緒に歌える、というところがうまくいったのだと思います。その辺りからCMが動き出したというか、どんどん日本の懐かしい歌を出そうということになって、『結婚しようよ』という僕の大好きな吉田拓郎氏の曲も使ったりして制作していきました。
内藤:そして、2003年に「イー、アール(一、二)」という作品も制作されています。

葛西:ハルビンで撮影しました。これも安藤隆さんのコピーです。2001年に9.11の同時多発テロが起こって、世界中が失意にあるようなときでした。いつしかロングセラーとなったウーロン茶も、今年、新たな気持ちで出発するぞ、というような気持ちも込めました。ならば、「一、二」というコピーなので、元旦から広告を打つのはどうだろうという、そんな順序でだんだん形になっていきました。一歩二歩、とか、一人よりは二人のほうがいいぞとか、踏み出そうという気持ちですね。
内藤:ウーロン茶の仕事で、葛西さんにとって財産だなと感じられることはどのようなことですか。
葛西:生活することやその日常のささやかな喜び、ちょっとしたことで今まで寂しい顔した人が少し笑ったとか、誰かと気持ちが通じたとか、そういうことに心が動くことを発見させてくれたと思います。人の原始的な感覚というのか…。
登場する人はほとんどが一般の人たちです。たくさんの人をオーディションしていて、いいなと思う人は、女の子であろうが男の人であろうが、ただドーンと真正面を向いて、素直に立っている人です。何にも染まっていない無垢な姿で。そういう人についつい惹かれてモデルに抜擢していましたね。
だいたいロケ本番は1週間から10日くらいかかりますが、撮影が進むにつれて彼らがどんどん変化していくのを目の当たりにしました。言葉は通じなくても、カメラの前でその人から自然に生まれたしぐさに、こちらがシャッターを押すと、そのことをこちらが喜んでいるということがモデルに伝わり、生き生きとした表情が生まれてくる。言ってみればだんだんスターになってくる。そのことで僕らがまた撮影に熱中していく、というような… 何かに触れたような感じがしました。
できれば、この僕らが経験した中国での出会いや出来事みたいなものを、まるごと生け捕りにして日本に帰って映像としてお茶の間に流したら、きっと見る人も何か感じてくれるんじゃないか、ということを信じていました。
だから、当初のプレゼンテーションと出来上がりが違うことがよくありました。約束が違うじゃないかということの連続でした。だけど、結局それが編集して形になったりポスターになったりして「いや、いいかもしれない」と思ってくれたのは、広告主として出来たものを見ているのではなく、普段生活している1人の人として、「やっぱりいいんじゃないか」と思ってくれたということだと思います。そういう思いが通じて形になっていくということを、この仕事のおかげで実感することができたと思います。
内藤:そういうふうに制作されたからこそ、見ている方も幸せな気持ちなる。日常をいとおしく感じるということですよね。
葛西:ええ。何か事件を起こすわけでもなく、物語でもなく、その場のシーンだけがそこにあって。その場にあった心の動きが、見ている人たちに伝わったのだと思います。
ヒロシマ・アピールズ

内藤:2013年の『ヒロシマ・アピールズ』が、今でも葛西さんにとっては大切な、忘れられないお仕事だそうです。演題のキーワードにもなっていますが、「伝わる」ためにはどんなことを心掛けていらっしゃるのか、という核心に迫れればと思います。
葛西:JAGDAから1年に1人グラフィックデザイナーが選出され、『ヒロシマ・アピールズ』というタイトルでB全サイズのポスターを作るというテーマです。もう20回以上続いており、広告ではない取り組みです。
指名を受けて、僕が自分の職業として何ができるかを考え悩み、とにかく広島を想う気持ちをどのように表現しようかと思ったとき、僕が子どもの頃から聞いてきたことの1つが、原爆が投下され戦争が終わったときは真夏ですごく空が晴れていたというイメージです。
僕自身は北海道生まれなので、夏がとても短い。その少ない快晴の時に空を見るとすごくまぶしい、という風景が頭に浮かんできました。子どもの頃は坊主頭だったので、そのときの自画像みたいなものが頭に浮かんだのです。
この絵は、もしかしたら視線の向こうの空に爆撃機が飛んでいるのを見ている、と受け取られるかもしれませんが、何か自分の中に大切なものを胸に抱えて空を見上げているというのが絵を描いた意図です。デザイナーですから、『ヒロシマ・アピールズ2013』をいいタイポグラフィで文字を組もうとか、ポスターらしくしようみたいなことを考えてしまいそうになるのですが、この時だけは自分の職業を忘れて、とにかく広島のことや亡くなった人のことを想って、自分の大切な人のことを想うということだけを頭に描きながら紙に筆で描いてみて、同じ絵を4日間くらいかけて何十枚も描いて、その中から自分としてのベストワンを選んで大きく伸ばしたものです。
内藤:今もご自宅のリビングに飾られて、毎日朝食のときにこのポスターを見ながらお食事をされると伺いました。
葛西:あまり自分の仕事のポスターなどを部屋に飾ることはしないのですが、このポスターに限っては額装して飾っています。朝食のときに椅子に座るとちょうど真正面に見えましてね。毎日いろいろな物事が起こっても、このポスターを見ると「負けないぞ」みたいな気持ちになれて。「このままで終わるものか」、とか、自分で作ったものなのに、何か次につなげるための活力を与えてくれるものがありまして。コーヒーを飲みながら、「今日もやるか」というような気持ちになったりします。そういう励みになるので、自分の中でも不思議な位置づけにありますね。
内藤:葛西さんが、「伝わる」ために心掛けていらっしゃることってどんなことですか?
葛西:うーん… 内藤さんはどうですか?

内藤:私がNHKに新人で入ったときに言われていたのは、「伝わるためにはまず思いが大事」だと。伝えたいという思い。でも、思いだけでは伝わらないし、技術がないといけない。だから「技術と思いは両輪だ」と教わって育ってきました。その教えは常に根底にあります。
どうしたら伝わるのだろう、この思いを伝えたい。でもそこに技術的なもの、伝えるためのアナウンスメントの技術が土台にないといくら思いだけがあっても伝わらないので、その両輪が大切であると。とても難しいことなのですが。
葛西:今、教わった気がします。
僕も広告の技法などは学んだわけではなくて、学んでいないからこそ、人からお金をもらってする仕事なのだから、技術、例えばタイポグラフィでもちゃんと言葉が伝わる、ちゃんと読める、最低限のそういう技術を身に付けないとデザイナーとしてやっていけないだろうと思ってきました。アイデア以前のそういうことを、若い頃は一生懸命やっていましたね。いつかこの技術さえあれば、技術を通して、伝えるための思いが加われば、たくさん盛り込まなくても相手に伝わるはずだということを信じていました。内藤さんの話を聞いて再確認できました。
内藤:やはり新人のときに言われたことをよく覚えています。「アナウンサーとして、自分の中に言葉の水瓶を貯めなさい、言葉の水瓶を絶やさないようにしなさい」と言われたこともとてもよく覚えており、修業の日々だと今でも思っております。
最後に葛西さん、これからの広告の果たす役割についてなど、是非メッセージをお願いします。
葛西:本当に難しいです、今の時代は。デジタルとかデータの重要性は分かった上での話ですが、それでも実感するのは、作っている人も見る人もやはり人間で、ヒトという動物は原始的なものにも通じる、ものすごい感知能力・感受性というようなものを持っていると思います。あまりたくさん喋らなくても、相手を信じて何かを渡すと相手は感じてくれるはずだと思います。あまり説明過剰・装飾過剰にならずに、少し物足りないくらいのものを目の前に差し出すと、相手が同情してくれて何を言おうとしているんだろう?ということでついつい耳を傾けてくれるような気がします。めったに喋らない小さな声の人って、聞いてみると、よくいいことを言いますね。そういうコミュニケーションの力もあるはずだと思うので、もっと人の持っている能力、相手を信じる力っていうものを発揮したほうが、効果があるんじゃないかなと思ったりします。
これは天野祐吉さんが引用されていた言葉で、初出がどなたかわからないのですが、「想像力とは何かというと、それは常識というもので歪んでしまった現実を元に戻そうとする力である」という難しいことを紹介されておられました。“常識というもの”で歪んでしまった、そこでいう“常識”って何か?と僕も想像するのですが、「今の常識はこうだろう」と、実際には時代時代で常識は変わるということを言っているのかもしれないですね。だけどそれによって歪められた“現実”というものがあって、想像力というのはその歪められた現実を本来の姿に戻そうとするものであると。すごく言い得ているというか、すごいことを指摘している言葉だと思いました。
ですので、改めて想像力というのは素晴らしいものだと思うのです。これからの広告でも、やはり相手の想像力に委ねる、その人を、見る人を信じることができれば、きっと広告は力を持つことができるのではないか、と最近は考えています。
内藤:葛西さん、本日は本当に大変貴重なお話をありがとうございました。